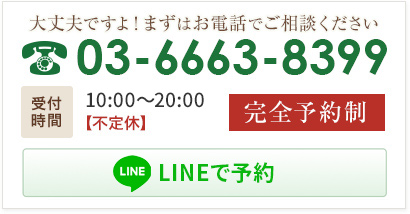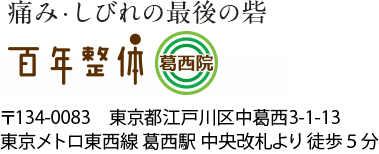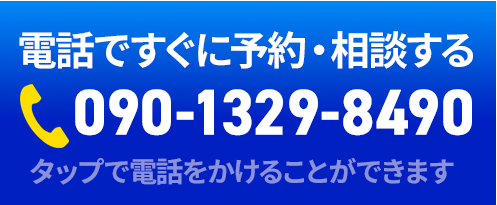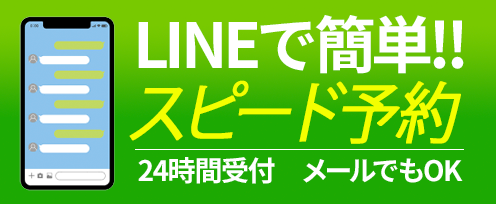こんにちは(^^)/
百年整体葛西院です
「朝、なかなか起きられない」
「学校に行きたい気持ちはあるのに、体が動かない」
これは、怠けているわけでも、気持ちの問題でもありません。
起立性調節障害は、自律神経のバランスが乱れることで、立ちくらみや朝の不調が起きる歴とした体の不調です。
整体師としてたくさんのご相談を受ける中で、「毎日のちょっとした習慣」でお子さんの体調が少しずつ安定していく姿を何度も見てきました。
今回は、ご家庭でできる生活習慣のコツを5つご紹介します。
① 朝日をしっかり浴びる
朝の太陽の光には、体内時計をリセットする効果があります。
起立性調節障害の方は、体内リズムが夜型になってしまっていることが多く、これが朝の不調の一因に。
*ポイント*
起きたらまずカーテンを開けて、部屋に朝日を取り入れる。
雨の日や冬は「光目覚まし時計」などを使うのも◎
ポイントは、体を起こす前でもOKということ。
お布団の中でも、目に光が入ることで体内リズムに働きかけてくれます。
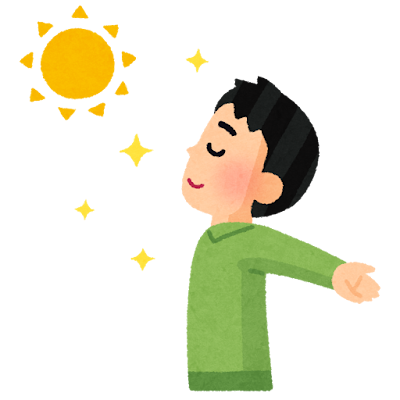
② 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
「昨日は夜中までゲームして、今朝はお昼まで寝ていた」
という生活が続くと、体のリズムはどんどん乱れていきます。
特に起立性調節障害のあるお子さんは、自律神経のリズムが崩れると、症状が強く出やすいため注意が必要です。
*ポイント*
まずは就寝時間を固定することからスタート!(起床時間は少しずつ整える)
週末も平日と大きくズレないように意識する。
睡眠のリズムが整うと、朝の起きやすさにも変化が見えてくることがあります。

③ 水分と塩分を意識的に摂る
起立性調節障害では、血圧の低下や血液循環の不安定さがよく見られます。
水分や塩分をしっかり摂ることで、血流が改善し、立ちくらみや倦怠感の軽減が期待できます。
*おすすめの摂り方*
朝起きたらコップ一杯(200ml)の水を飲む(冷たすぎない常温水がおすすめ)
食事で塩分を適度に摂る(みそ汁、梅干し、お吸い物などが◎)
《子どもの一日の食塩摂取量の目安》
| 年齢 | 男の子・女の子
|1~2歳| 3.0g未満
|3~5歳| 3.5g未満
|6~7歳| 4.0g未満
|8~9歳| 5.0g未満
|10~11歳| 6.0g未満
|12~14歳| 7.0g未満
・・・
※※※ 注意点 ※※※
・これは「食塩相当量」です。
(ナトリウム量とは異なります)
・加工食品や外食には多くの塩分が含まれている場合があるので注意が必要です。
・子どもは大人よりも腎機能が未熟なため、塩分の摂りすぎには特に注意が必要です。
水分は一日1.5〜2リットルを目安に。
スポーツドリンクのような塩分を含む飲料も、体調に応じて取り入れてみてください。

④ スマホ・ゲームは夜20時まで
寝る直前までスマホやゲームをしていると、脳が覚醒状態になり、寝つきが悪くなってしまいます。
ブルーライトは「眠くなるホルモン(メラトニン)」の分泌を抑えてしまうため、特に注意が必要です。
*ポイント*
それ以降は読書や音楽、ストレッチなどでリラックスタイムに切り替える。
最初は嫌がるかもしれませんが、習慣になってくると、子ども自身も「朝がラクになった」と実感してくれることが多いです。

⑤ 無理に頑張らせない。「今日は無理でも、明日またやってみよう」でOK
起立性調節障害は、日によって体調の波が大きいもの。
「せっかく昨日は登校できたのに、今日はまた無理…」
そんなとき、親として焦りや不安を感じるのは当然のことです。
でも、無理に頑張らせることが逆効果になるケースもあります。
*大事にしたい考え方*
小さな「できた!」を一緒に喜ぶ。
今日は無理でも、「また明日やってみようね」と声をかける。
比べない、責めない、寄り添う。
お子さんのペースで回復していくことが、長い目で見たときに一番の近道になります。

まとめ
焦らず、生活リズムを少しずつ整えていきましょう。
起立性調節障害の改善には、「生活習慣の見直し」がとても大切です。
ただ、一気に全部を変えるのは難しいと思いますので、まずは朝の光を浴びることから始めてみてください。
当院では、ただ施術をするだけでなく、お一人おひとりのお話を丁寧にうかがいながら、その方に合った生活のアドバイスを行っています。
「体のことも、生活のことも相談できて安心した」と感じていただけるよう、心を込めてサポートしております。
もしお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね♪